睡眠剤 デメリット 常用は避けるように注意することが大切です。睡眠剤は不眠の際に服用するケースもあると思いますが、常用は危険ですので中しなければいけません。
睡眠剤 デメリット
人間の体には、本来病気になったときには、自然に治療するための機能が備わっています。病気の中には、薬に頼らなくても自然と治るものがあります。
風邪をひいたときに自然治癒力だけに頼っていたら、何にも学校を休んだり、会社を休まなくてはなりません。
めまぐるしく時間に追われている生活の中では、こうした方法を選ぶことができません。
そんなわけで薬に頼るのですが、薬の中には副作用を招くものがいくつかあります。
副作用とはいかなくても、胃腸に負担をかけてしまったり、食欲不振といった症状がでることもあります。
薬を服用する際には、医師の指示に従うことが原則です。
不眠になってしまうと、すぐに睡眠剤を飲むことを考える人がいますが、これによる常習性や中毒の危険があります。
睡眠剤についての危険な点、副作用を医師や薬剤師の指示に従えば危険性は、大きく減らすことができます。
ただし、自分だけの判断で漠然と飲み続けたり、量を増量したりすると、睡眠剤がやめられくなったり、悪循環を招いて中毒になってしまったりします。
不眠症は、眠れない原因をしっかり突き止めるのが最優先です。また、不眠症の大半が精神的負担や不眠恐怖症によるものです。
これらを取り除くための行動が需要です。
入眠・熟眠のために薬を用いる前にどうしたら安眠できるかを考えてみましょう。
現在、不眠治療で主に使われる代表的な薬やその副作用について詳しいページがありますのでこちらも熟読することをおすすめします。こちらです。
睡眠剤 デメリット まとめ
睡眠薬の常用には、以下のような様々なデメリットや注意点があります。
常用を避けるべき主なデメリット・リスク
- 依存性(身体的・精神的依存):
- 特定の種類の睡眠薬(ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の一部など)を長期間(特に数週間以上)続けて服用すると、薬がないと眠れないという状態になったり、薬を減らしたり中止した際に離脱症状(反跳性不眠、不安、頭痛、手の震えなど)が出ることがあります。これを常用量依存と呼ぶこともあります。
- リバウンド不眠:薬をやめた直後に、服用前よりも強い不眠が生じる現象です。
- 副作用(翌日への持ち越し効果):
- 翌朝まで眠気やふらつき、倦怠感が残ることがあり、日中の集中力低下や転倒、交通事故のリスクを高めます。特に作用時間が長い薬で起こりやすいです。
- 耐性:
- 長期間の使用で、同じ量では効果が薄れてしまい、さらに薬の量を増やさなければ効かなくなることがあります。
- 認知機能への影響:
- 特に高齢者では、物忘れやふらつき、転倒のリスクが高まるほか、せん妄(意識が混濁し、幻覚などが見られる状態)のリスクも指摘されています。一部の研究では、特定の睡眠薬の長期使用と認知症との関連性が示唆されていますが、結論は得られていません。
- 異常行動(奇異反応):
- まれに、服用後に意識がもうろうとした状態で、夢遊病のように異常な行動をとる(食事をする、運転するなど)ことが報告されています。
常用を避けるための注意点
- 医師の指示を厳守する:
- 処方された用法・用量を必ず守り、自己判断で量を増やしたり、急に中止したりしてはいけません。
- 効果が感じられない場合は、自己判断で追加服用せず、医師に相談してください。
- 休薬・減薬は慎重に:
- 睡眠薬を中止する際は、離脱症状を避けるため、必ず医師と相談しながら、時間をかけて徐々に減らしていく(漸減療法)ことが大切です。
- アルコールとの併用を避ける:
- 睡眠薬とアルコールを一緒に飲むと、薬の作用が強く出すぎたり、記憶障害、呼吸抑制、翌日の眠気・ふらつきなどのリスクが非常に高まります。寝酒も睡眠の質を低下させるため避けてください。
- 眠れない原因への対処も行う:
- 睡眠薬はあくまで「対症療法」であり、不眠の根本的な原因(生活習慣、ストレスなど)を治すものではありません。
- 規則正しい生活習慣(毎日同じ時間に起きる、適度な運動、寝る前のカフェイン・喫煙を避けるなど)や、認知行動療法といった薬以外の方法を並行して行い、薬の早期中止を目指すことが重要です。
睡眠薬は、正しく使えば不眠のつらい症状を緩和し、生活の質を改善する助けとなりますが、漫然とした長期連用は避けるべきです。服用について不安や疑問がある場合は、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
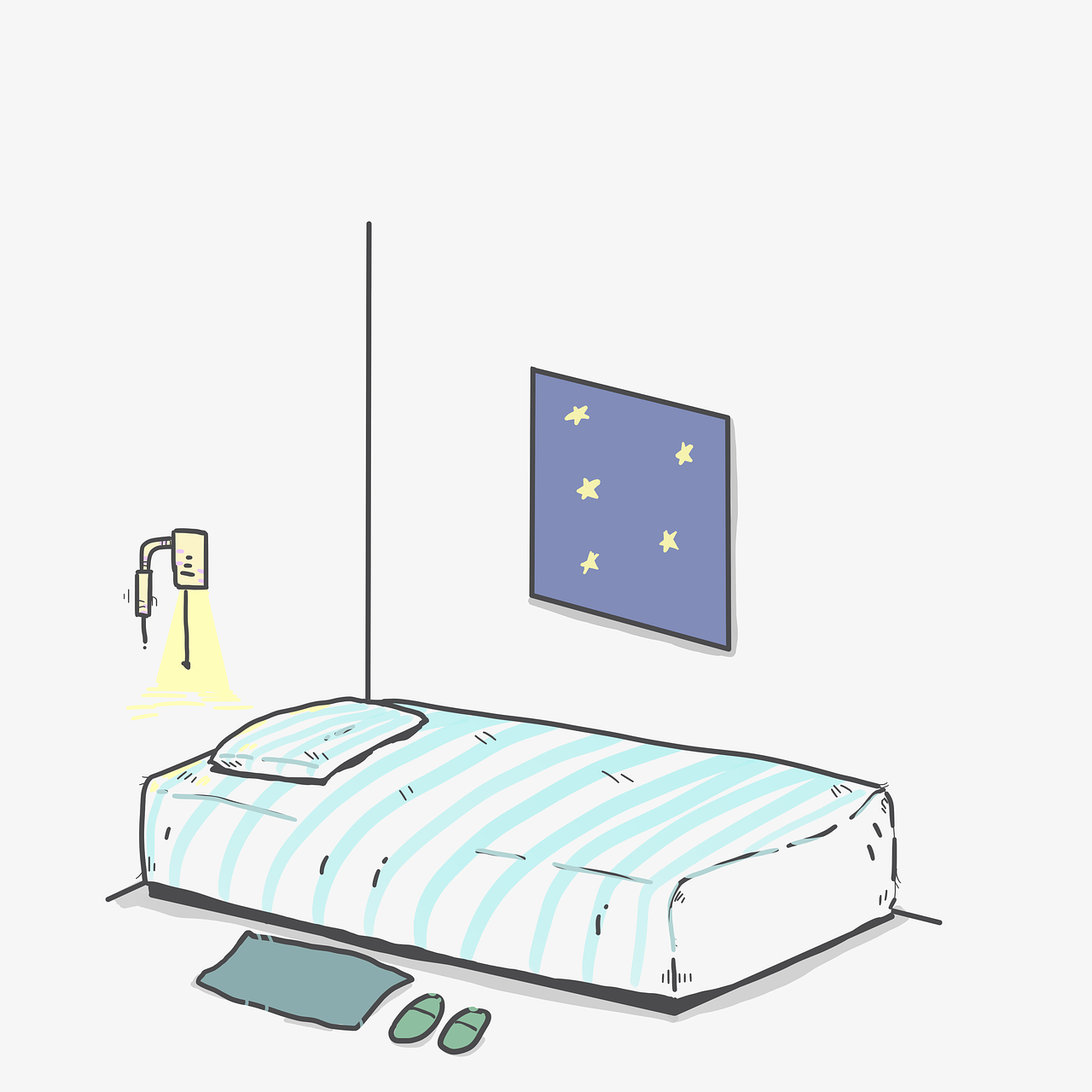


コメント