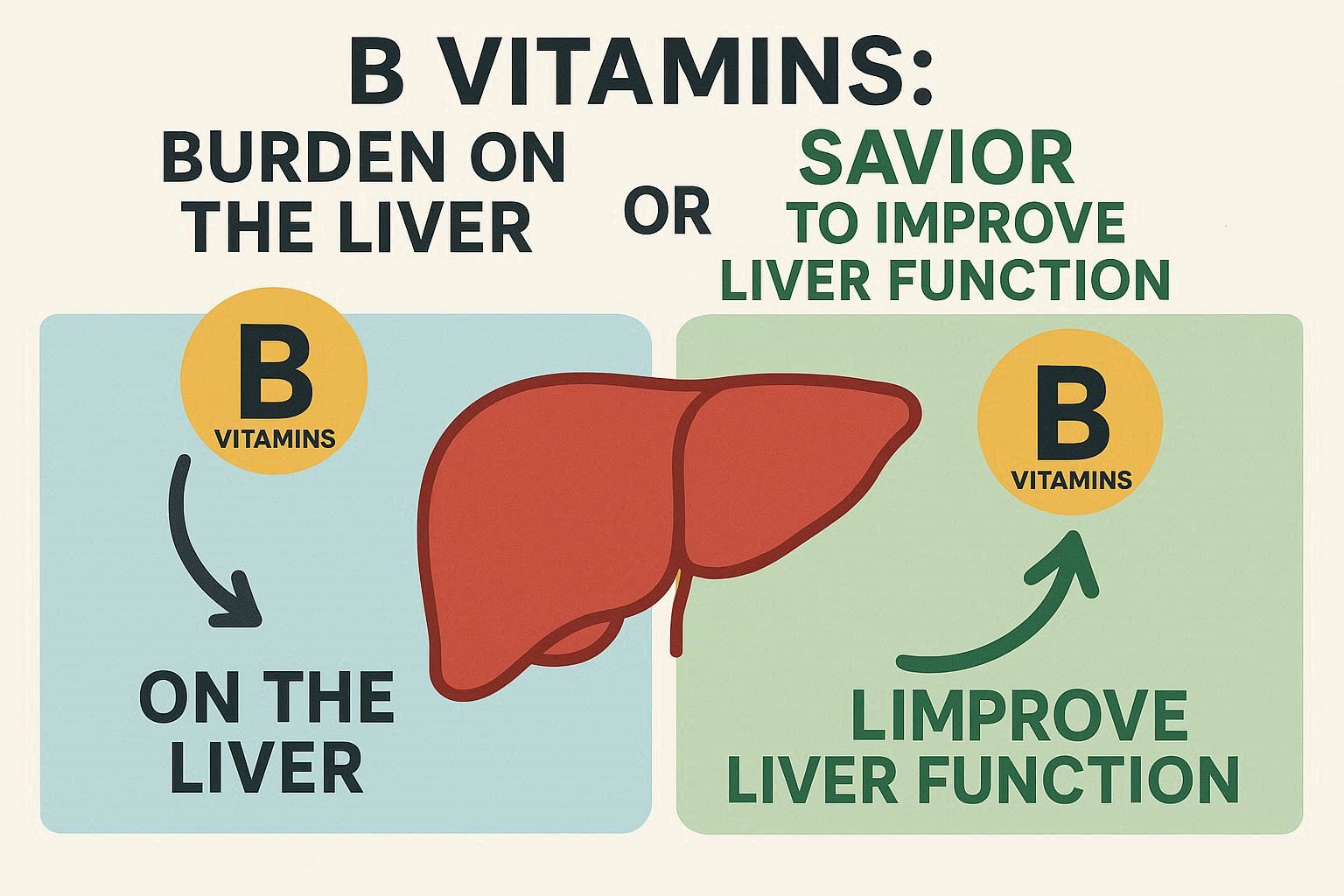ビタミンB群 肝臓 に負担?それとも肝機能アップの救世主でしょうか。このビタミンB と肝臓の関係性についての誤解を解消していきたいと思います。
【誤解を解消】 ビタミンB群 肝臓 に負担?それとも肝機能アップの救世主?
ビタミンB群は「肝臓のビタミン」とも呼ばれるほど、アルコール代謝やエネルギー生成といった肝機能に不可欠な栄養素です。
しかし、一部では「サプリメントの摂りすぎは肝臓に負担をかける」という話も聞かれ、混乱しがちです。
この記事では、ビタミンB群が肝臓にとって「救世主」なのか、それとも「負担」になり得るのか、その両側面を科学的な視点から解説し、正しい摂取の知識をわかりやすくお伝えします。
そもそもビタミンB群と肝臓の関係には、「救世主」としての働きと、過剰摂取による負担という2つの側面があります。適切に摂取すれば肝機能の正常化や向上に役立ちますが、一部のビタミンでは摂りすぎに注意が必要です。
【救世主としてのビタミンB群】
-
肝機能の正常化・向上: ビタミンB群(特にB1、B2、B6、B12など)は、アルコールの分解や糖質・脂質・タンパク質の代謝に欠かせない補酵素として働きます。
-
アルコール分解のサポート: アルコールを分解する過程でビタミンB群が大量に消費されるため、飲酒量が多い人ほど不足しやすく、適切な補給は肝臓の負担軽減につながります。
-
脂肪肝の予防: ビタミンB2やコリンなどは脂質の代謝を促し、肝臓に脂肪が蓄積するのを防ぐ働きが期待されます。
-
肝細胞の再生: ビタミンB2は肝細胞の再生を促進するとされています。
-
【負担となる可能性(過剰摂取に注意が必要なもの)】
-
ビタミンB群は水溶性で、基本的に余分は尿として排出されますが、一部のビタミンをサプリメントなどで大量摂取すると副作用が報告されています。
-
ナイアシン(ビタミンB3): 大量摂取により皮膚の紅潮、嘔吐、下痢、肝機能障害が起こる可能性があります。
-
ビタミンB6: 長期間にわたる過剰摂取で、手足のしびれや痛みなどの神経障害を起こす可能性があります。
-
葉酸: 合成葉酸を大量摂取した場合、発熱やじんましんなどが報告されています。
-
【結論と誤解の解消】
-
通常の食事や、医師・管理栄養士の指導に基づく適量摂取であれば、ビタミンB群は肝臓にとって救世主であり、機能維持と向上を助けます。
-
「肝臓に負担」という誤解は、特定のビタミンをサプリメントなどで過剰摂取した場合の副作用リスクから生じたものです。
したがって、ビタミンB群は肝臓の働きを支える重要な栄養素ですが、摂取目安量を守り、過剰摂取を避けることが大切です。