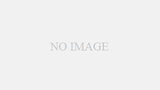膵臓がん 最新治療 現在の治療の方法や現状、症状、治療など。自覚症状などを紹介します。すい管造影で世界最小のがんを発見することも可能になっている膵臓がんについての最新情報です。
膵臓がん 基礎知識
- 日本人には少なかったがんですが、食生活の変化などにより著しく増加しています。
- ほかの消化管(十二指腸など)に近い膵臓の頭部に起こりやすいです。
- 男女比は2対1で、男性に発生しやすいです。
- 60歳代がもっとも多く、高齢者は特に注意が必要です。
- 膵炎や糖尿病などは、がんとは直接的な因果関係はありません。
- 多くの場合、がんによる二次的な膵炎を併発しています。
- 目立った自覚症状は痛みで、特に背中から腰にかけての痛みが現れます。
- 急激な体重減少や黄疸が出ることも多いです。
- 直径2cm以下で被膜内のものであれば、5年生存率は約50%に達しています。
- 手術中の放射線照射(術中照射)によって、痛みをやわらげることが可能になりました。
どこに起こるがんなのか
膵臓は、胃の裏側にあるバナナ状の細長い臓器です。体の中央に近く、十二指腸と接している右側が太く、左に行くほど細くなります。太い部分を「頭部」、中央部分を「体部」、細くなって脾臓と接している部分を「尾部」と呼びます。
この膵臓には2つの働きがあります。1つは消化液のひとつである「膵液」を作る働きで、これは十二指腸に分泌され、食物の消化に利用されます。もう1つは、血液中の糖(血糖)の量を調節するホルモン(インスリンとグルカゴン)を作る働きです。
膵臓がんは、十二指腸に近い頭部に起こりやすく、約7割が頭部から体部にかけて発生し、残りの3割が体部から尾部にかけて発生します。体の奥深くにある臓器のため、がんができても発見や治療が難しいのです。欧米諸国では、膵臓がんが見つかっても根本的な治療を行わないケースも少なくありません。
しかし、診断技術や治療法の進歩により、多くの症例が治せるようになってきました。特に日本は早期発見や手術方法において世界をリードする成績を上げています。早期に発見できれば、不治の病ではなくなりつつあります。
どのような人に起こりやすいのか
消化器系のがんの中では、胃、肝臓、大腸に次いで4番目に多く、年々増加しています。年間の死亡者数は1万人を超えています。昭和35年から56年の比較では、約2.5倍に増加しています。
男性の発症率は女性の2倍です。発症のピークは60歳代であり、高齢者に多いがんと言えます。原因として慢性膵炎や糖尿病などが引き金とされてきましたが、最近では否定されています。欧米で多く、日本では比較的少なかったことから、動物性脂肪の過剰摂取が原因とされ、酒やたばことの因果関係も否定できません。
自覚症状
膵臓がんは初期には自覚症状がほとんどなく、発見が遅れることが多いです。ただし、進行すると以下のような症状が現れます。
膵臓がんの患者の約4分の3は、なんらかの痛みを感じます。急激な痛みと鈍痛があり、進行するほど痛みが強くなります。痛みは背中から腰、上腹部、左の肋骨の下などに現れます。筋肉に異常がないのに強い痛みがある場合は、注意が必要です。
体部や尾部にがんが発生すると、急激な体重減少が見られます。消化機能の異常や痛みによる食事量の減少が原因です。ほかの消化器に異常がないのに体重が急減する場合は、膵臓がんを疑う必要があります。
膵臓の頭部にがんがある場合、黄疸が出ることもあります。痛み、体重減少、黄疸のほかに、全身倦怠感、発熱、下痢、吐き気などが現れることもあります。
診断方法
膵臓がんは「膵液」の通り道である「膵管」に近い場所に発生したものほど症状が出やすいです。ここにがんができると膵液の流れが悪くなり、その滞りから異常をつかむ診断法が開発されました。アミラーゼやエラスターゼといった膵臓の酵素の血中濃度を測定する方法です。
異常が見つかれば、膵管に造影剤を入れてX線撮影を行います。この「膵管造影」は技術が向上し、かなり小さながんまで発見可能になっています。膵管造影によって直径8ミリのがんが発見され、切除に成功した例もあります。これは世界でも最小の膵臓がんの発見・治療記録です。
膵臓がんは膵炎を併発していることが多く、「膵炎」と診断された場合は、念のために膵管造影を受けることが望ましいです。検査は10分程度で終わります。膵炎によって膵管が拡張し膵臓全体が硬くなると、胃が圧迫されます。これは胃のX線撮影でも分かるため、偶然に早期の膵臓がんが見つかることもあります。
どこまで治るのか
膵臓がんの治療成績は著しく向上しています。直径2センチ以下のがんであれば、5年生存率は約50%に達しています。胃がんなどと比べると低く見えるかもしれませんが、これは非常に良好な数字です。
膵臓は他の消化器に囲まれ、血管やリンパ管も複雑に入り組んでいるため、手術が非常に難しいのです。さらに、がんは小さくても内部に深く進行し、リンパ節や神経などに浸潤しやすいという特性があります。こうした悪条件の中での50%という数字は、評価に値します。
膵臓がんの多くは、他の臓器に浸潤したり、リンパ管を通じてリンパ節に転移しやすく、また進行も速いです。がんが直径3センチを超えると、長期生存は難しくなります。
ただし、全体の1割を占める「粘液産生がん」は、比較的浸潤が少なく進行もゆっくりしています。このタイプは、以前は「慢性膵炎」と診断されていた例も多いです。とはいえ、早期発見・早期治療は必要です。
治療は切除が中心となりますが、膵臓がんの手術は非常に難しいとされています。頭部にできたがんでは、十二指腸と一緒に切除する必要があり、この手術には約5時間かかります。体部から尾部のがんでは、尾部側をすべて切除します。
膵臓がんの自覚症状とその説明
| 症状 | 説明 |
|---|---|
| 上腹部や背中の痛み | 膵臓は胃の裏側にあり、がんが進行すると背中まで痛みが及ぶことがあります。 |
| 体重減少 | 食欲低下や栄養の吸収障害により、急激に体重が減少します。 |
| 食欲不振・吐き気 | 胃腸の圧迫や消化機能の低下が原因となることがあります。 |
| 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる) | 膵頭部のがんが胆管をふさぐことで発生します。 |
| 便の色が薄くなる(白っぽい) | 胆汁の流れが妨げられることで、便が白っぽくなります。 |
| 糖尿病の急な悪化または新たな発症 | 膵臓のインスリン分泌が障害され、血糖値のコントロールが乱れます。 |
| 全身のだるさや倦怠感 | がんの進行により体力が奪われ、慢性的な疲労感を感じやすくなります。 |