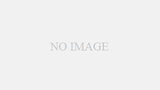舌癌 症状 をはじめとした口・鼻のガンを治すポイントを紹介します。男性に多い原因はどこにあるのでしょうか。舌癌 はヘビースモーカーに多いことから男性の方に多く見られます。
口・鼻のガンの状況

舌癌 症状
- 口では舌癌、鼻では上顎洞がんが多く、いずれも男性に多い。
- 舌癌は舌の側縁部に発症するものが大半で、そこが硬くなっていたら赤信号。
- ヘビースモーカー、酒飲みは舌のがんになる危険度が高い。
- 舌がんは放射線治療がとてもよく効き、初期ならそれだけで治ることが多い。
- 鼻のがん(上顎洞がん)は自覚症状は出にくいが、鼻の片詰りや鼻汁がおもな自覚症状である。
- 蓄膿症や慢性的な副鼻腔炎が上顎洞がんになることがある。
口・鼻のガン
口に発生するがんで圧倒的に多いのは舌がんで、口のがんの約6割を占めます。舌がんによる死亡者数は、2002年時点で1147名と、30年前の2.7倍にまで増加しており、男性のほうが女性の約2倍も多いです。
鼻のがんの9割以上を占めるのは上顎洞がんで、鼻のがんといえばこれを指すほどです。かつては年間1000人以上の死亡者がありましたが、減少傾向にあります。これも特に男性に多いです。
舌癌
およそ9割が舌の側縁に発生します。また、側縁でもやや後方で、舌を前に出さないと見えないような部分に多い傾向があります。男性に起こりやすいのは、お酒やタバコに関係があるためです。
このがんが非常に多いインドやスリランカでは、タバコの葉にビンロウジュの実や石灰を混ぜてムのようにかんだり、火のついた葉を口に入れて吸う習慣があり、タバコが原因であるという説が有力です。
また、お酒の飲みすぎが原因であるという説も強くあります。さらに、歯との関係も深いです。虫歯で欠けた歯の角や、治療で装着したブリッジが舌に刺激を加え続けることで、がんを起こすことがあります。舌の側縁に多いのは、そのためといわれています。口内の不衛生も誘因とされています。
舌癌 症状 (自覚症状)
初期では、熱いもの、冷たいものを食べると、舌、とくに側線部がしみる。もう少し進行すると、傷もないのに舌の特定の部分が痛む。
さらに進むと表面が崩れて出血したり、口臭が強くなったり、また強い痛みが続く。
舌の一部が白い(白坂症)は、舌がんの初期か前がん状態の可能性がある。舌がんでは、がんの部分が硬くなる。舌は傷がついても硬くなることは少ないので、異常を感じた部分が硬いかどうかががんの判定材料になる。
舌は誤っかて噛んで傷つけることが多いため、がんを見過しやすい。痛みがあったが半年も放置していたという人も多い。
舌癌 診断
初期では、熱いもの、冷たいものを食べると、舌、とくに側線部がしみる。もう少し進行すると、傷もないのに舌の特定の部分が痛む。
さらに進むと表面が崩れて出血したり、口臭が強くなったり、また強い痛みが続く。
舌の一部が白い(白坂症)は、舌がんの初期か前がん状態の可能性がある。舌がんでは、がんの部分が硬くなる。舌は傷がついても硬くなることは少ないので、異常を感じた部分が硬いかどうかががんの判定材料になる。
舌は誤っかて噛んで傷つけることが多いため、がんを見過しやすい。痛みがあったが半年も放置していたという人も多い。
表在型は、比較的進行が遅く、進行しても深くまで達しない傾向にある。全体の約6割を占めるのが外方性増殖型で、患部に硬いコブを作ることが多く、周囲が白くなりやすい。
もっとも大きさの割には内部に浸潤することは少ない。3割が、内部に深く浸潤する内方浸潤型だが、たいした症状がないままに内部に深く広がる。。
舌の筋肉の深くにまで入り込むと、舌が動かなくなったり、舌の神経麻痺をおこすおそれがある。舌がんは、治療技術が進歩しており治るがんになりつつある。
直径2センチ以下の初期なら5年生存率は、8割~9割に達しており、舌の根元にまで進んだり下顎の骨に食い込んだ中期でも3~4割パは助かっている。
もっとも進行すると、命は助かっても舌を全部摘出することが少なくない。がんが4センチ以下なら放射線治療だけでよく治り、手術でも舌の全部摘出は避けられるので、早期発見が重要。
放射線治療は、針状容器に放射線の一種、ラジウムをつめたものを、がんを取り囲むように刺し込んでおく方法が早くからおこなわれ、効果があがっている。がんを放射線で格し子状に取り囲み、とろ火で焼き殺すのだと考えていい。この治療は1週間で終る。がんが4センチ以上になったものでは、手術になることが多い。Ⅲ期以上の進行がんでは舌を縦半分切除することが多いが、がんの広がりぐあいによっては、舌のほかに頬や顎まで切除しはおあごなければならないこともある。
舌がんは約半分が転移するので、Ⅲ期やⅥ期の進んだものの手術では舌の切除とともに頸部のリンパ節も同時に郭清することが多い。
舌を切除すると日常生活に大きな支障が出るので、再建手術があわせておこなわれる。体の皮膚の表を血管をつけたまま切り取り、舌の欠けた部分を補てんするのである。
切除が舌の半分までなら再建手術で完全に社会復帰ができる。また、舌を完全に摘出しても、軟らかいものなら食べられるようになるし、会話も理解できるていどまで回復が可能だ。
上顎洞がん
上顎洞がん が起こる場所、なりやすい人などを紹介します。また、上顎洞がん 症状 についても。
上顎洞がんが起こる場所
鼻の奥には、とても大きな空洞が広がっている。これを副鼻腔と呼ぶ。副鼻腔の内側は粘膜でおおわれているが、風邪などで炎症がおこりやすい。また、副鼻腔に慢性的な炎症が続いているのが蓄膿症(副鼻腔炎)である。副鼻腔は大小いくつかの部屋に分かれているが、最大の空洞が上顎洞である。
鼻の奥の両側面、目の下、ちょうど頬の骨の奥にある。上顎洞がんは、この上顎洞の壁の粘膜にできる。
上顎洞は顔の両側にあるが、がんは両側同時にできることはきわめて少ない。
上顎洞がんになる人
鼻のがんの約9割が上顎洞がんで年間約700~1000人あまりが死亡しているが、死亡者数は年々減少している。これは、治療技術の進歩もあるが、発生率が減少していることが大きい。
年代では50~60歳代に多いが、男性の発生率は女性の1,5倍にのぼる。この男女差の理由は不明。上顎洞がんは欧米に少なく日本に多い。そのため、日本人の鼻の構造ががんになりやすいのではと考えられている。
日本人は鼻が低く、鼻腔がやや上を向いている人が多いので、粘膜刺激物を吸い込みやすいためとされる。
また、慢性的な刺激や炎症もがんの危険因子である。たとえば、慢性副鼻腔炎や蓄膿症を放置しておくと、がんになるおそれがある。昔はよく「あおばな」をたらした子どもをよくみたが、あれは蓄膿症の症状なのである。はなたれ小僧の減少とともに、上顎洞がんも比例して減少。
上顎洞がんの自覚症状
初期の自覚症状ほはとんどありません。しかし、自覚症状が現れたときほかなり進行している。奥の方に増殖すると三叉神経を圧迫し、の歯の痛みが出るので虫歯と間違えやすいのが危険です。
顔の前方に増殖すると目の下の頬がはれる。ひどくなると、お岩さんのような容貌になる。顔の方に向かうと眼球を押しあげるので、眼球の位置が左右で異なります。
鼻の奥に増殖すると鼻汁といっしょに血膿が出たり鼻がつまるが、この症状は蓄膿症と区別がつきにくい。もっとも蓄膿症は両方の鼻に同じ症状が出るが、ガンは片方だけのことが多いです。
表在型は、比較的進行が遅く、進行しても深くまで達しない傾向があります。全体の約6割を占めるのが外方性増殖型で、患部に硬いこぶを作ることが多く、周囲が白くなりやすいです。
もっとも、大きさのわりには内部に浸潤することは少ないです。3割は内部に深く浸潤する内方浸潤型ですが、はっきりとした症状がないままに深く広がってしまうことがあります。
舌の筋肉の深くにまでがんが入り込むと、舌が動かなくなったり、舌の神経麻痺を起こすおそれがあります。舌がんは、治療技術が進歩しており、治るがんになりつつあります。
直径2センチ以下の初期であれば、5年生存率は80~90%に達しています。舌の根元にまで進んだり、下顎の骨に食い込んだ中期のケースでも、3~4割の方は助かっています。
もっとも進行すると、命が助かっても舌をすべて摘出することが少なくありません。がんが4センチ以下であれば、放射線治療だけでもよく治り、手術でも舌の全摘出を避けることができるため、早期発見が非常に重要です。
放射線治療では、針状の容器に放射線の一種であるラジウムを詰め、それをがんを取り囲むように刺し込む方法が早くから行われ、効果を上げています。がんを放射線で格子状に囲み、とろ火で焼き殺すようなイメージです。この治療は、1週間で終了します。
がんが4センチ以上になった場合は、手術になることが多いです。Ⅲ期以上の進行がんでは、舌を縦に半分切除することが多く、がんの広がり具合によっては、舌のほかに頬や顎まで切除しなければならない場合もあります。
舌がんは、約半数が転移するため、Ⅲ期やⅣ期といった進行した状態では、舌の切除とともに頸部のリンパ節も同時に郭清(かくせい)することが多いです。
舌を切除すると、日常生活に大きな支障が出るため、再建手術があわせて行われます。体の皮膚を血管をつけたまま切り取り、舌の欠けた部分を補うのです。
切除が舌の半分までであれば、再建手術によって完全に社会復帰が可能です。また、舌を完全に摘出しても、軟らかいものであれば食べられるようになりますし、会話もある程度まで理解できるレベルに回復することが可能です。
上顎洞がんの診断
頻のはれ、歯の痛み、鼻井汁の膿などの症状を聞き、頬や口の中を観察し、触れてみれは、ほぼ診断がつく。がんの疑いが濃厚ならⅩ線による撮影によって診断を下す。また、蓄膿症の手術のときに、偶然にがんが発見されることがある。
治療による効果
これまでは発見の遅れが多く、死亡率も高かったのですが、治療法が進歩したことで、生存率はおよそ5割前後にまで向上しました。長い間、上顎洞部をすべて摘出する治療が主流でしたが、この手術は難易度が高く、治療成績もあまり良くありませんでした。
手術では、顔の皮膚を大きく切開し、上顎の骨を切り離してから摘出します。しかし、顔の奥には重要な神経や血管が複雑に走っており、それらを傷つけずにきれいに取り除くことは、きわめて困難でした。
そこで最近では、放射線療法や抗がん剤による化学療法でがんを小さくしてから摘出する手術が、効果を上げています。
化学療法では「動注療法」がよく用いられています。耳の前を通っている動脈にカテーテル(細い管)を通し、そこから抗がん剤を注入して上顎洞がんを治療する方法です。
このような治療法の進歩により、手術後の日常生活への影響も少なくなってきました。かつては上顎洞の手術を受けると、悲惨なほどの容貌の変化を覚悟しなければなりませんでしたが、現在では、そのような外見の変化もかなり防げるようになってきています。