機能性不眠 常習性不眠 の徹底解説:あなたの不眠の原因と今日からできる対策を紹介します。試験前日や仕事で大事なプレゼンがあるようなときは、よく眠れませんね。眠れた…と思ったらすぐに目が覚めてしまったりします。旅行に行って寝具がいつもと異なるような場合にも眠れないのは、こうしたケースと同様です。
機能性不眠 常習性不眠 の徹底解説
「機能性不眠」や「常習性不眠」という言葉は、医学的な正式名称ではありませんが、一般的に慢性不眠症の状態を指すことが多いです。
本解説では、特定の身体的・精神的な病気が原因ではないにもかかわらず、生活習慣や誤った睡眠へのこだわりによって長期化してしまった不眠(機能性不眠が長期化した常習性不眠に近い状態)に焦点を当てます。
あなたの不眠の原因を特定し、今日から実践できる**生活習慣の改善(睡眠衛生)**や、不眠の悪循環を断ち切るための具体的な対策を徹底的に解説します。質の高い睡眠を取り戻すための一歩を踏み出しましょう。
こうした不眠は、「機能性不眠」といい、一種の不眠にかわりありませんが、心配することはありません。試験や大事なプレゼンが終わったり、旅行から帰宅すれば、また眠れるようになります。
こういった場合には、無理に寝ようとしないで「思い切って朝まで起きている」というぐらいの気持ちでいたほうがかえってストレスになりません。
次に何か特別なことがないのに、眠れない!「常習性不眠」です。これを一般的に不眠症と呼んでいます。
その原因は、さまざまで環境や体の痛み、かゆみなどの症状、脳の器質障害、精神神経症、老化、本能性高血圧症などがあります。
これらの原因の中にも危険なものとそうでないものとがあります。
心配しすぎて眠れない人もいるので、気を付けなければなりません。
「不眠ノイローゼ」「不眠恐怖症」などが不眠患者の大部分を占めることからも不眠症に神経質になりすぎるのは、よくありません。
不眠症もタイプがあり、それぞれに特徴があるので、自分にあてはまるものがないかどうかをしっかり把握します。
神経症の人に多い「睡眠障害」タイプ
このタイプは、寝ようと布団に入ってもなかなか寝付けないタイプです。寝ようとして、トイレに行ったり、本を読んだり、お茶を飲んだりして余計に眠れなくなるタイプです。ひどくなると寝酒や睡眠剤を使ってやめられなくなてしまうことが多くあります。
神経症の人に多くみられ、眠りにつくと朝寝坊するくらいよく眠ります。
夢を見て眠れない「熟眠障害」タイプ
夢が原因でよく眠れない…と言うのが口グセです。悪夢が多く、不快で目を覚ますと、汗をかいている場合が多いです。実際は、夢を見ているので、眠れていないわけではありません。悩みや不安などがあると、悪夢を見やすいといいます。気持ちの上での解決方法が重要になります。
こうした人は短時間睡眠のほうが体を休めることができます。
鬱病も潜む「早朝覚醒」タイプ
このタイプの不眠はとても心配な不眠です。背後に鬱病が潜んでいるケースが多いです。
寝付きはいいのですが、夜中や明け方に目が覚め、それから眠れないことが多く困ります。
不眠以外にも、疲れや食欲不振、毎日が憂鬱でつまらなく感じます。
もう少しひどくなると、被害妄想や自殺願望が芽生えます。これは、専門医の診断を受けなければなりません。
よかれと思って家族が励ましたりしてかえって症状を悪化させるケースもあるので、家族も正しい知識を身につけなければ成りません。
素人判断で不眠を治そうとせずに、専門医の受診をしましょう。
これらのタイプが複合的に重なる場合もあります。不眠症の人が不眠を目の敵にしてしまう傾向がありますので素人判断せずに病院を受診しましょう。
不眠は、眠れないというだけで起こるわけではありません。病気が陰に潜んでいて原因になっていることもあります。
「機能性不眠」や「常習性不眠」という言葉は、医学的な診断名として一般的に使われるものではありませんが、慢性的な不眠症を指していると考えられます。
一般的に不眠症は、原因や期間によって分類され、特定の病気や身体的問題が原因でない不眠が「機能性不眠」や「一次性不眠症」として表現されることがあります。また、不眠が長期化して生活の一部になっている状態を「常習性不眠」と呼ぶ場合もあります。
ここでは、最も関連性の高い慢性不眠症(原因不明の不眠が3ヶ月以上続くもの)を中心に解説し、その原因と対策を紹介します。
不眠の原因となる可能性のある要因
不眠は単一の原因ではなく、さまざまな要因が複合的に絡み合って起こることがほとんどです。
1. 心理・精神的な要因
- ストレスや不安: 仕事や人間関係、生活環境の変化による緊張や不安で寝つきが悪くなることがあります。
- うつ病や適応障害: 気分や感情の障害が不眠の症状として現れることがあります。
2. 生理的な要因
- 生活習慣の乱れ: 不規則な睡眠・起床時間、夜型生活、休日の寝だめなどは体内時計(概日リズム)を乱し、不眠の原因になります。
- 加齢: 年齢とともに睡眠が浅くなり、中途覚醒や早朝覚醒が増える傾向があります。
3. 環境的な要因
- 寝室の環境: 光(スマホやPCのブルーライトも含む)、騒音、温度、湿度が不適切だと質の高い睡眠が妨げられます。
4. 身体的な要因
- 体の病気: 痛みや痒み(アトピー性皮膚炎など)、頻尿、咳、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群など、さまざまな身体疾患が不眠を引き起こすことがあります。
5. 薬や嗜好品による要因
- カフェインやニコチン: 覚醒作用があるため、夕方以降の摂取は避けましょう。
- アルコール(寝酒): 一時的に寝つきは良くなるものの、睡眠の後半で覚醒を促し、睡眠の質を低下させます。
今日からできる具体的な対策(睡眠衛生の改善)
不眠の改善には、薬に頼る前に、まず生活習慣(睡眠衛生)を見直すことが基本です。
1. 睡眠・起床のリズムを整える
- 毎日同じ時刻に起床する: 休日も含めて朝決まった時刻に起きることで体内時計がリセットされ、夜自然な眠気が訪れやすくなります。
- 朝の光を浴びる: 起きたらカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。体内時計を調整する最も効果的な方法です。
- 昼寝は短く: 昼寝をする場合は午後3時まで、30分以内に抑えましょう。長すぎると夜の睡眠に悪影響を与えます。
2. 寝る前の行動と環境を見直す
- 寝室を快適に: 室温、湿度、寝具を調整し、暗く静かな環境を作りましょう。
- 寝る前の刺激を避ける: 就寝前の1〜2時間はスマホ、PC、テレビの使用を避けましょう。ブルーライトが睡眠を促すメラトニンの分泌を抑制します。
- リラックスタイムを設ける: ぬるめの入浴(就寝の1〜2時間前)、軽い読書、穏やかな音楽などで心身の緊張をほぐしましょう。
- 寝酒はしない: アルコールは睡眠の質を悪化させます。
3. 日中の活動を見直す
- 適度な運動: 夕方など就寝の3時間以上前にウォーキングなどの適度な運動を取り入れると睡眠の質が改善されます。
- カフェインやニコチンを控える: 午後以降のコーヒー、紅茶、エナジードリンク、喫煙は控えましょう。
4. 眠れない時の対処法
- 床から離れる: 15〜20分経っても眠れないときは、「寝なければ」というプレッシャーから解放されるため、一度寝室を出て、リラックスできる場所で過ごし、眠気を感じてから再び床に戻ります。
- 時計を見ない: 時間を気にするとストレスになり、さらに眠りを遠ざけます。
専門家への相談
上記の対策を1〜2週間継続しても不眠が改善しない場合や、日中の生活に支障がある場合は、専門家への相談を検討してください。
- 睡眠専門医・精神科・心療内科: 不眠症の診断と治療(睡眠導入薬の適正な使用、認知行動療法など)。
- 内科: 身体的な病気が原因の不眠を調べる。
不眠症の治療では、間違った認識や不安を取り除く認知行動療法が非常に効果的です。専門医と協力して根本的な改善を目指しましょう。
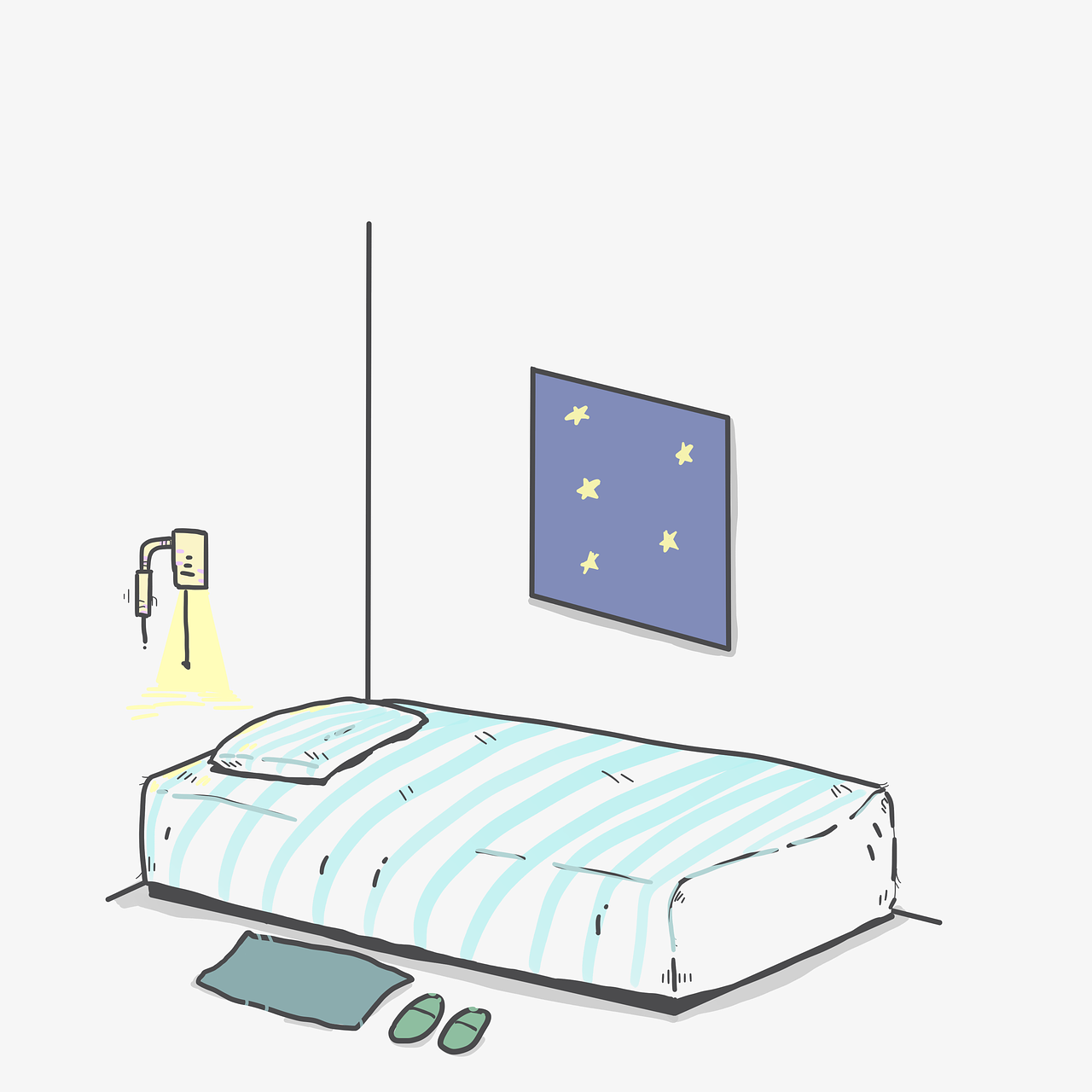


コメント