寝酒 デメリット 「過ぎたるは、なお及ばざるが如し」という言葉がぴったりです。昔から安眠、快眠の手段として、「寝酒」が愛用されてきました。酔うとほかほかして気持ちよくなり、眠くなく作用を利用しているものです。
アルコールには、神経の興奮を鎮静させる作用があります。このは、脳の働きを抑制する作用がアルコールに含まれるためで、この鎮静作用がイライラを鎮め、入眠の助けになります。
寝酒 デメリット
「寝酒は寝つきを良くする」と考える人は多いですが、これは大きな誤解です。寝酒は一時的に眠気を誘うものの、睡眠の質を大きく低下させ、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。質の良い睡眠を得るためには、就寝前の飲酒を避けることが重要です。
お酒が好きな人にとっては、喜ばしいことですが、寝酒が慢性的になり、アルコールがないと眠れなくなり、アルコール中毒になってしまう場合もあります。
アルコールの入眠促進作用は、個人差があり、このことは、アルコールの量が少なくても酔ってしまう人と、大量に飲んでも酔わない人との差によく似ています。
また、アルコールを飲むと興奮してしまい、逆に眠れなくなってしまう人もいます。これは、普通アルコールは脳の働きを抑制するのですが、これが解法されてしまうと、逆に興奮状態を引き起こすためです。
つまり、少量のアルコールで眠れる人は、寝酒の力を借りてもかまいませんが、かなりの量を飲まないと眠りにつけない人は、避けたほうがいいのです。
少量なら害がないといっても、やなりアルコールに頼ることはあまりよくありません。
就寝前に飲んでしまうと、アルコール分解のために肝臓が働かなくてはならなくなり、体が休まらないのです。
満腹は眠れないでも書きましたが、胃腸が休まらないために眠れないのと同じです。
寝酒をやめようとして、不眠に悩まされる人が多いのも、寝酒をあまりすすめられない理由でもあります。
これは、睡眠剤をやめるときと一緒でしばらくの期間、苦しい場合が多いのです。
寝酒をやめる場合には、少量ずつ減らしていくのが体にも脳にも負担がかからずにいいでしょう。少量のアルコールで穏やかに入眠できても実際の脳の睡眠状態を調べたら、浅い眠りである人が多かったという調査結果もあります。
入眠に使うお酒は、精神的緊張を和らげる、少量にしておくのが正しい使い方であることをしっかり覚えておきましょう。
寝酒 デメリット まとめ
寝酒(就寝前のアルコール摂取)は、一時的に眠気を誘い「寝つきが良くなる」と感じることがありますが、実際には睡眠の質を低下させ、様々なデメリットを引き起こします。
睡眠の質を低下させる
- 睡眠が浅くなる: アルコールは入眠を早める一方、睡眠の後半になると覚醒作用が働き、眠りが浅くなります。特に深いノンレム睡眠(脳と体を休める大切な睡眠)が減少し、レム睡眠(夢を見る睡眠)が増加します。結果として、睡眠時間は確保できても熟睡感が得られず、疲れが取れにくくなります。
- 夜中に目が覚めやすくなる: アルコールが体内で分解される過程で交感神経が刺激され、心拍数や体温が上昇します。これにより夜中に目が覚めやすくなり、トイレが近くなることも中途覚醒の原因になります。
- いびきや無呼吸症候群が悪化する: アルコールはのどや舌の筋肉を緩め、気道が狭くなるため、いびきが悪化したり、睡眠時無呼吸症候群を悪化させる可能性があります。
体に与える悪影響
- 耐性がつきやすい: 繰り返し寝酒を続けると、同じ量では眠れなくなり、徐々に飲む量が増えてしまいます。これはアルコール依存症への入り口となる可能性があり危険です。
- 脱水症状を引き起こす: アルコールの利尿作用により、就寝中に体内の水分が失われやすくなります。脱水症状は翌日のだるさや頭痛の原因になります。
- 肝臓に負担をかける: アルコール分解のため肝臓は休むことなく働きます。長期的には肝機能障害のリスクを高めます。
睡眠の専門家からの見解
多くの睡眠専門医は、質の良い睡眠を得るために寝酒を避けるべきだと推奨しています。寝酒は不眠の根本的な解決策にはならず、悪循環に陥るリスクがあります。
睡眠の質を上げるための代替案
- 就寝2〜3時間前には飲酒を終える。
- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる。
- 軽いストレッチや瞑想を行う。
- カフェインを多く含む飲み物(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)は夕方以降控える。
寝酒をやめられず不眠が続く場合は、専門の医療機関に相談することをおすすめします。
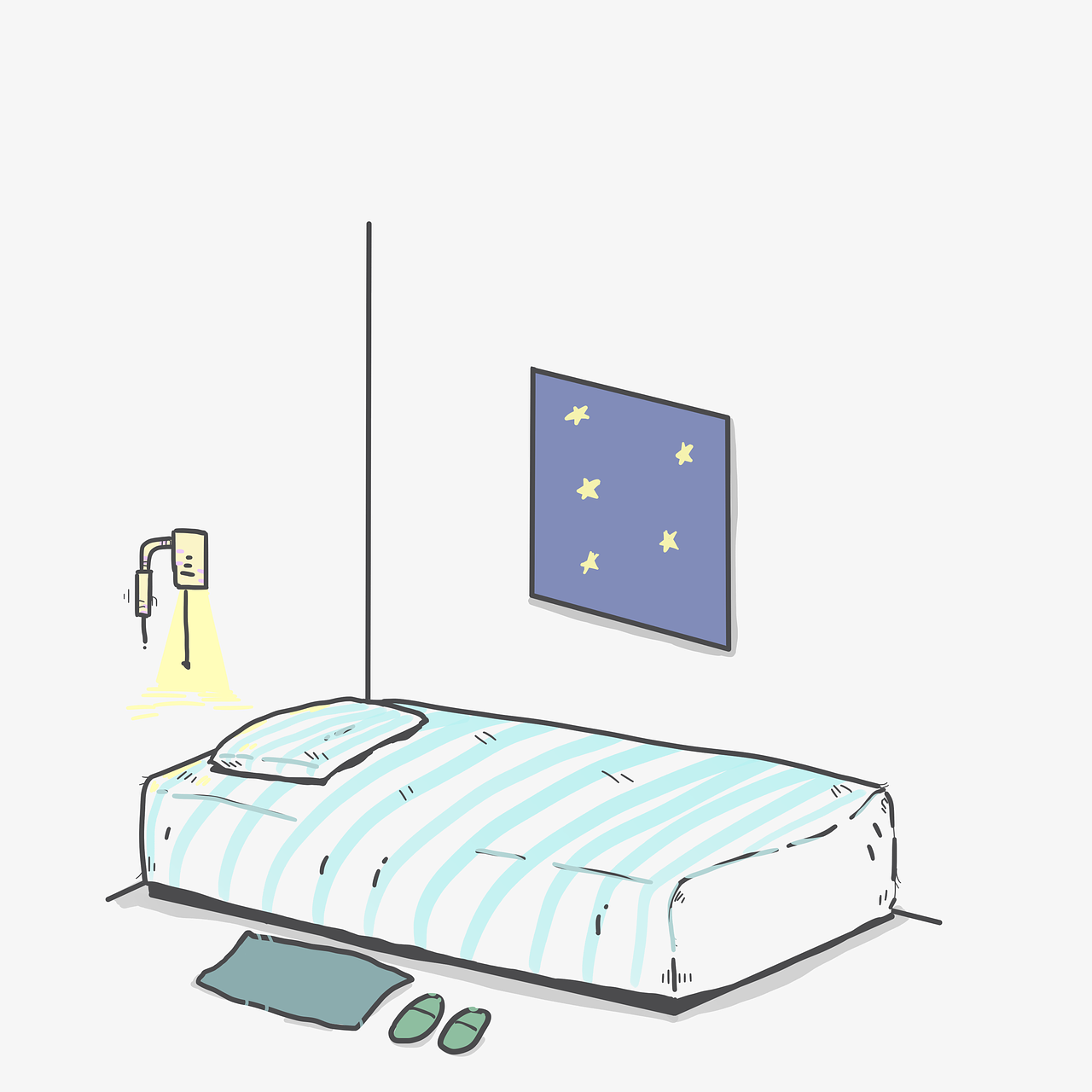


コメント