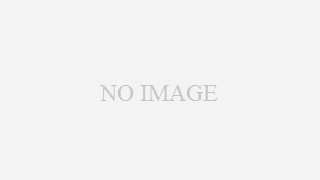 内臓脂肪
内臓脂肪 ぽっこりお腹は、見た目以上に血管と全身を老けさせる
ぽっこりお腹は、見た目以上に血管と全身を老けさせる という情報です。30 代 ~ 40 代あたりから油断をすると、つい増えてしまうお腹まわりの脂肪。久しぶりに会った知り合いに「あれ、なんだか貫禄がでてきたねぇ!」なんてやんわりと指摘されて、...
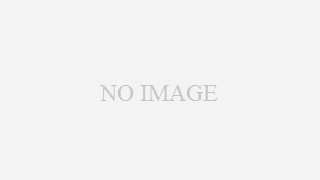 内臓脂肪
内臓脂肪 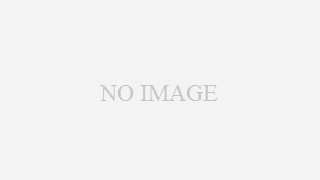 内臓脂肪
内臓脂肪 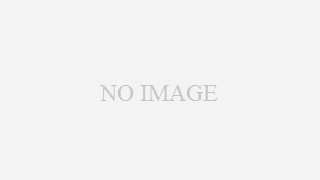 内臓脂肪
内臓脂肪