抗てんかん薬 頭痛 に効く種類は 頭部神経痛、片頭痛、群発頭痛です。いくつかの抗てんかん薬は、頭痛を改善する効果があるとされています。たとえば、トプラマイト(トピラマート)という抗てんかん薬は、片頭痛の予防にも使用されることがあります。その他の抗てんかん薬にも頭痛の緩和効果がある場合がありますが、個別の薬剤によって異なる可能性があります。
抗てんかん薬 頭痛 に使用する場合は予防だけでなく痛み止めとしても使われる
抗てんかん薬は、もともとてんかん発作の原因となっている、脳の神経細胞の異常興奮を抑える薬です。抗てんかん薬が効くといっても、その頭痛がてんかんによるものというわけではありません。
ただ、てんかん発作と近い状態が脳神経細胞で起こっているためなのです。それぞれのタイプの頭痛に対する作用は次のとおりです。
頭部神経痛に対する作用
頭部神経痛のビリビリする痛は、末梢の神経細胞の異常興奮だと考えられています。この興奮を鎮めるのです。抗てんかん薬を飲むと、過半数の人が痛みが消えるか、軽減しています。
片頭痛と群発頭痛に対する作用
脳の異常興奮を起こす神経の細胞は、セロトニンと関連していると考えられています。片頭痛や群発頭痛もまた、血液中のセロトニンの増加やその働きと関係があることがわかっています。抗てんかん薬の作用によってセロトニンの働きが弱められると、細胞の異常興奮も抑えられます。とくにパルプロ酸ナトリウムは、片頭痛や群発頭痛にも効果があり、予防薬として使われます。
主な抗てんかん薬
- バルプロ酸ナトリウム
- カルバマゼピン
- クロナゼパム
抗てんかん薬の効果
頭部神経痛の人は
痛み止めのために飲みつづける必要がある。長期間服用する場合は副作用の心配があるので、とくに中高年の人は肝機能検査を定期的に受けること。
片頭痛の人は
毎日定期的に飲むことによって、頭痛発作の回数が少なくなる。ただ、効果が現れるまでには最低でも1ヶ月ほどかかるので、すぐに効果が出ないからといって、勝手に服用を止めてしまわないこと。
群発頭痛の人は
毎日定期的に飲む必要がある。すぐれた効果が得られた人がいる反面、効かなかったという人もあり、効果に大きな差があることを理解しておく。
抗てんかん薬は急性の副作用として眠けが出やすいので、仕事などにさしつかえるときは医師に相談する。
関連リンク:てんかん

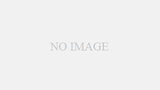
コメント