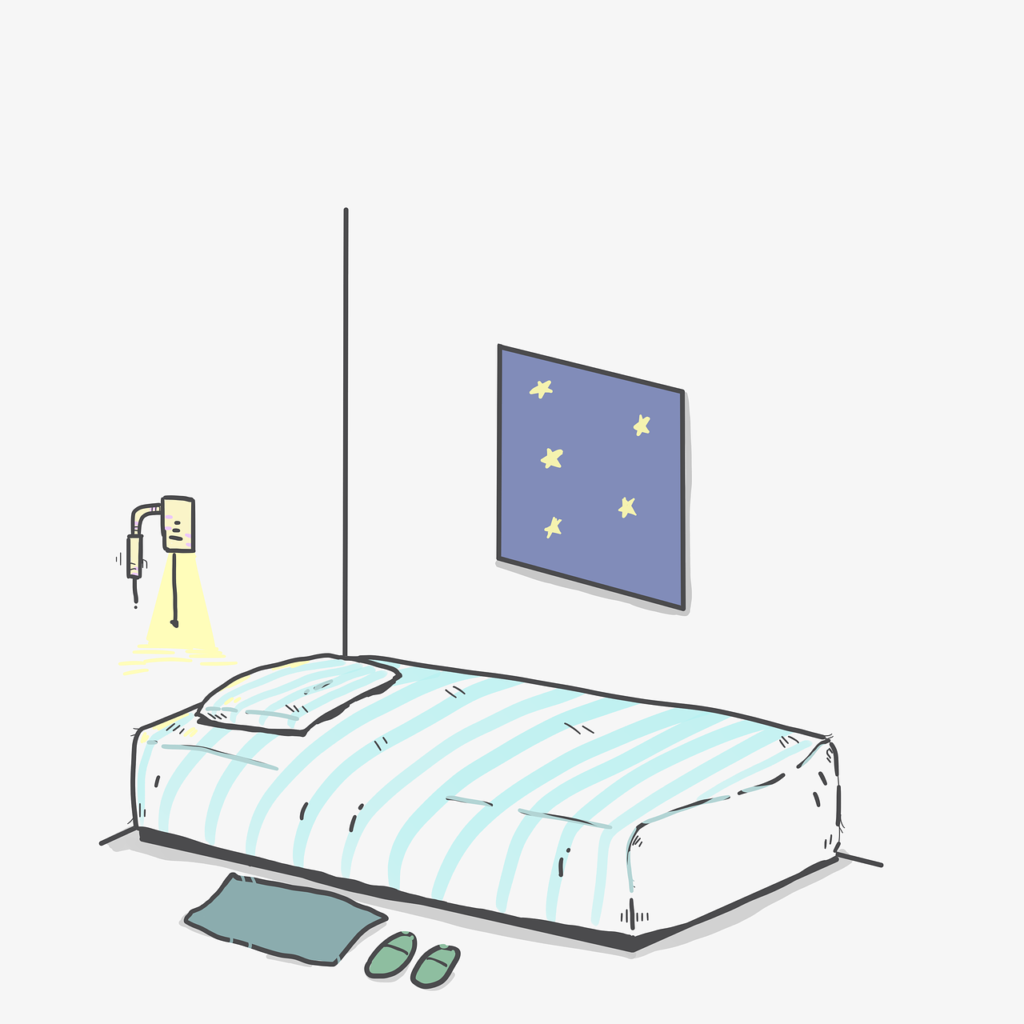寝過ぎ 倦怠感 解消 するにはどうしたらいいでしょうか。疲れた時など、少しいつもより睡眠時間を多くとって目覚めると体がいつもよりかなりだるく感じたりしませんか?
寝過ぎ 倦怠感 解消 するには
長時間の睡眠が、かえって体にだるさや重い倦怠感をもたらすことがあります。
「たくさん寝たはずなのに、なぜか体がだるい…」
そんな経験はありませんか?実は、これは「寝過ぎ」が原因かもしれません。
この記事では、寝過ぎによる倦怠感の原因を解き明かし、その解消法を具体的にご紹介します。今日からできる簡単な対策で、すっきりと気持ちの良い一日を取り戻しましょう。

寝過ぎ 倦怠感
寝過ぎによる自律神経の乱れが身体を重くしてしまうのです。休日に寝坊して、いつもよりも長時間寝たのにもかかわらず、よけいに身体にだるさを感じることがありますよね。寝ることで身体を休めているはずなのに、どうして寝すぎるとだるくなるのでしょうか。
睡眠と覚醒には、「睡眠ホルモン」と呼ばれるメラトニンなどのほかにも、自律神経である交感神経と副交感神経が重要な働きをしています。
交感神経はおもに身体を活動的にする働きがあり、副交感神経は身体をリラックスさせて睡眠へと導く働きがあります。これらふたつが適切に働くことで、睡眠と覚醒という 1 日の生活リズムができるのです。
つまり、寝る直前まで身体を活動的にする交感神経のほうが優位に働いていると、目が冴えてなかなか眠れないのです。いっぼう、睡眠中は副交感神経が優位に働いているが、寝坊していつもより寝すぎてしまうと、本来起きている時間にまで副交感神経の優位な状態がつづき、十分な覚醒ができなくなるのです。
その結果、だるさを感じてしまうのです。
姿勢や寝相の悪さも「倦怠感」の原因
寝起きにだるさを感じる原因には、寝ているときの姿勢が関係している場合もあります。寝ているときは、どうしても同じ姿勢でいることが多く、寝相が悪いと、身体の特定の部分に負担がかかりやすくなります。そのため、腰や肩などの血行が悪くなり、疲労が蓄積することがあります。そうなると、起きたときに疲労感やだるさの原因になります。
寝起きに倦怠感を感じ、疲れがとれない人は、質の高い睡眠のチェックをしてみるといいでしょう。
寝過ぎ 倦怠感 解消 するには (まとめ)
1. 体内時計をリセットする
- 朝日を浴びる: 起きたらすぐにカーテンを開け、太陽の光を浴びましょう。光は体内時計をリセットし、覚醒モードに切り替えるスイッチの役割を果たします。
- 決まった時間に起きる: 平日と休日の起床時間に大きな差をつけないようにすることが大切です。休日でも平日プラス1~2時間程度にとどめ、体のリズムを崩さないようにしましょう。
2. 体を動かして血行を促進する
- 軽い運動をする: ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなど、血行を良くする有酸素運動が効果的です。体を動かすことで交感神経が優位になり、だるさが軽減されます。
- ストレッチ: 長時間の睡眠で固まった筋肉をほぐすために、首や肩、腰などをゆっくりとストレッチしましょう。血流が改善され、筋肉のこわばりが和らぎます。
- 温かいシャワーや入浴: ぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、全身の血行が良くなり、リラックス効果も得られます。
3. 食事と水分補給
- 朝食をしっかり摂る: 睡眠中はエネルギーが不足しがちです。起きたら炭水化物(ブドウ糖)を含むご飯やパンなどをしっかり摂り、脳と体のエネルギー源を補給しましょう。
- 水分補給: 起床時にコップ一杯の水を飲むことで、胃腸が活発になり、体の目覚めを促します。
- 疲労回復に良い栄養素を摂る: ビタミンB群(豚肉、うなぎ)、クエン酸(レモン、梅干し)、鉄分(レバー、ほうれん草)などを意識して摂ると、疲労回復に役立ちます。
4. その他の対策
- 短時間の仮眠を活用する: 日中の眠気が強い場合は、15時までに15分程度の短い仮眠を摂るのも有効です。ただし、長時間の昼寝は避けましょう。
- 寝具を見直す: 枕やマットレスが体に合っていないと、睡眠中に無理な姿勢となり、起きたときの倦怠感や体の痛みの原因になることがあります。
これらの方法を試しても倦怠感が続く場合は、他の病気(睡眠時無呼吸症候群やうつ病など)が隠れている可能性もあります。その際は、医療機関に相談することをおすすめします。
しっかり寝ているのに疲れがとれずにスッキリしない(活性酸素)