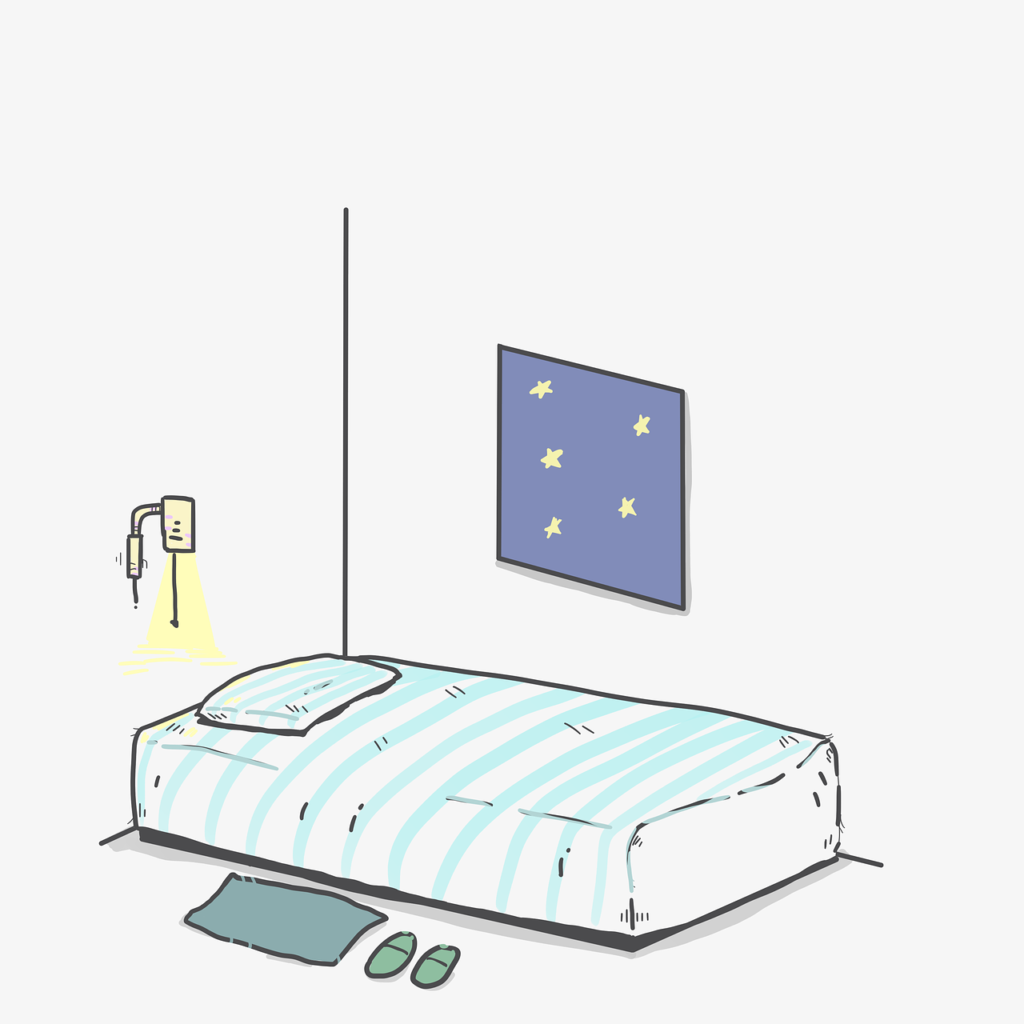睡眠と自律神経 夜中に目が覚める原因は?質の高い眠りを実現する整え方を紹介します。「夜中に何度も目が覚めてしまう」「朝起きたら疲れている」。これらの睡眠の悩みは、自律神経の乱れが原因かもしれません。
睡眠と自律神経
1. 睡眠中の自律神経の働きと「中途覚醒」のメカニズム
質の高い睡眠とは、副交感神経が優位になり、心拍数や体温、血圧が低下して心身が深くリラックスしている状態です。
質の高い眠り:副交感神経優位
理想的な睡眠では、入眠に向けて副交感神経が優位になり、深い眠り(ノンレム睡眠)に入ります。この間に疲労回復と心身のメンテナンスが行われます。
夜中に目が覚める原因:交感神経の過剰な活動
夜中に目が覚めてしまう「中途覚醒」の主な原因は、本来優位であるべき副交感神経ではなく、交感神経が活動しすぎていることにあります。
| 原因 | 自律神経の働き | 睡眠への影響 |
| ストレス・不安 | 脳が緊張状態にあり、夜間も交感神経が優位に働き続ける。 | 脳が覚醒モードのままで、眠りが浅くなり、夜中や早朝に目が覚める。 |
| 生活リズムの乱れ | 体内時計のズレにより、自律神経の切り替えリズムが崩れる。 | メラトニン(睡眠ホルモン)が適切に分泌されず、深い眠りに入りにくい。 |
| 寝る前の光・刺激 | スマホやPCのブルーライトが交感神経を刺激し、脳を覚醒させる。 | 寝つきが悪くなるほか、睡眠が浅くなり中途覚醒を引き起こす。 |
| 就寝前の飲食 | 食事や飲酒で消化器官が活発に動き、交感神経が刺激される。 | 体が休めず、内臓の働きが睡眠を妨げる。利尿作用による頻尿も原因に。 |
2. 質の高い眠りを実現する自律神経の整え方
日中の活動と夜の休息のスイッチをスムーズに切り替えるための生活習慣と就寝前のルーティンを紹介します。
1. 「光・食・活動」で朝のスイッチをオンにする
朝に交感神経をしっかりオンにすると、夜に副交感神経がスムーズに優位になります。
- 朝の光を浴びる: 起床後すぐにカーテンを開け、太陽光を浴びましょう。体内時計がリセットされ、睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌が抑制され、覚醒モードへの切り替えが促されます。
- 朝食をとる: 朝食は、体温を上げ、自律神経の切り替えスイッチとなります。簡単なものでもいいので、毎日決まった時間にとりましょう。
- 適度な運動: 日中に軽く汗ばむ程度の有酸素運動(ウォーキングなど)を行うと、適度な疲労感により夜の眠りにつながりやすくなります。
2. 就寝前の「副交感神経」優位な環境作り
寝る前の1~2時間で、交感神経を刺激するものを徹底的に避け、リラックスモードに切り替えましょう。
ぬるめの入浴で深部体温を下げる
- 就寝1~2時間前に、38℃~40℃のぬるめのお湯にゆっくり浸かりましょう。
- 体温が一時的に上がった後、体温が下がり始めるタイミングで自然な眠気が訪れ、深い眠りに入りやすくなります。熱すぎると交感神経を刺激するので注意が必要です。
スマホ・PCのブルーライトを遮断
- 寝る1時間前には、スマートフォン、パソコン、テレビを見るのをやめましょう。
- ブルーライトは脳を覚醒させ、メラトニンの分泌を強く抑制してしまいます。
深呼吸とリラックス
- 布団に入ったら、ゆっくりと深い腹式呼吸を数回行いましょう。息を長く吐くことを意識すると、副交感神経が刺激され、心身の緊張が和らぎます。
- クラシックやヒーリング音楽、好きな香りのアロマなどを取り入れるのも効果的です。
就寝前の飲食を控える
- 夕食は寝る3時間前までに済ませるのが理想です。
- アルコールは一時的に寝つきを良くしますが、睡眠後半の質を大きく低下させ、中途覚醒や早朝覚醒の原因になります。寝る前の飲酒は避けましょう。
睡眠中の不調を感じたら、「自律神経の乱れかも?」と考えて、まずは朝と夜のルーティンを見直すことが大切です。今日からできる小さな工夫で、質の高い眠りを取り戻しましょう。
自律神経は、体を活動モード(交感神経)と休息モード(副交感神経)に切り替えるアクセルとブレーキのような役割を担っています。この切り替えがうまくいかないと、夜間に体が休まらず、睡眠の質が大きく低下してしまうのです。
質の高い睡眠を取り戻すために、睡眠中の自律神経の働きと、そのバランスを整える具体的な方法を解説します。
人間には、生体リズムが働いていますが睡眠にもこの生体リズムは大きな影響を与えています。それとともに睡眠中にも自律神経機能の変化がみられます。以下にまとめてみました。
脈拍
ふつう、脈拍は1分間に70回くらいです。就寝してからだんだんと少なくなり、だいたい1分間に57回程度になります。
眠りに入ってだんだん深くなるノンレム睡眠のときに減少します。次に訪れるのが、レム睡眠時期です。レム睡眠時期になると、今度は、逆に増加します。1分間に65回前後になります。1回目のレム睡眠期が終わり、ふたたびノンレム睡眠期に入りますが、脈拍は、1回目のノンレム睡眠期よりもさらに減少し、1分間に55回くらいになります。
2回目のレム睡眠期に入ると、1回目のレム睡眠期より多くなります。一晩の眠りを追ってみるとレム睡眠は約90分のリズムをもって現れ、1回目と2回目とリズムを追っていくに従い増加が著しく現れます。
逆にノンレム睡眠期は、レム睡眠期に比べて脈拍は多いのですが、一晩のうちで大きな変動はみられません。脈拍は、一晩に1回の大きなリズムをもち、さらにレム睡眠の約90分のリズムによって変化する生体リズムを持っていることわかります。
呼吸
呼吸もノンレム睡眠期に少なくなります。そしてだいたい規則正しく行われています。ところが、レム睡眠期では呼吸数も多くなり、不規則になります。
レム睡眠期では、非常に速く成ったり一時的に止まったりという変化が現れます。呼吸が速くてい心配になる場合もありますが、これは、レム睡眠期の特徴で心配いりません。
血圧
血圧も脈拍や呼吸と同じような変化を現します。眠りにはいったときには血圧は下がり、朝方になると除々に上昇します。レム睡眠期には少し高くなり変動も同じように大きくなります。
体温
体温でも皮膚体温は、入眠のときに上昇することもありますが発汗などによってある程度調節されてたりします。しかし、一般的には、明け方に最も低くなります。血圧と同じで朝になると上昇します。
盗汗
盗汗には、精神性発汗と温熱性発汗とがあります。精神性発汗は、精神的に緊張のあったとっきに起こるものです。
一方、温熱性発汗は、気温と体温との差を調節するためにでるものです。
睡眠中では、精神性発汗はあまり変化はみられません。温熱性はっkなは、眠ってすぐに増加し、レム睡眠期に入ると少なくなります。
夜明けが近づくにつれて、少なくなり、レム睡眠が多くなる朝方にはかなり少なくなります。レム睡眠期には減少しますが、一時期的に増えることもあり、これは、悪夢をみているようなケースです。