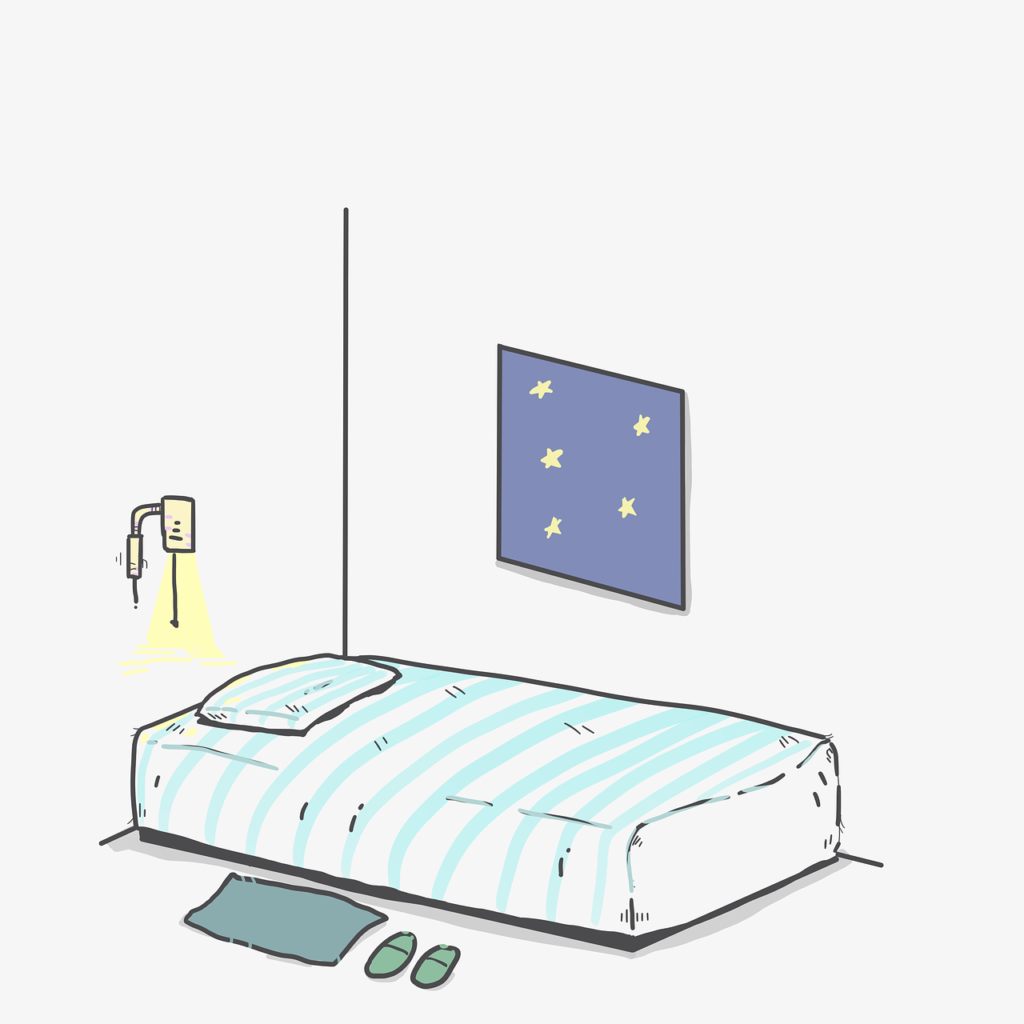眠れない人に 「 不眠症とは? 」 と聞くのは、あまりに無礼ですが、ここでは基礎知識から頭に入れていただきたいと思っています。
たとえば、眠れないにもいろんな種類があって
- 寝付きが悪い
- 夢をよく見ていて熟睡できない
- 夜中に何度も目を覚ましてしまう
などがあります。
長時間睡眠をとっても疲れがとれなかったり爽やかな目覚めでないときもあります。
よい眠りの条件は、
- 睡眠の質
- 睡眠の量
のふたつが満たされてはじめて満たされます。
睡眠の深さ、安定性、悪夢の有無、睡眠時間などです。
不眠症とは? 【不眠症の基礎知識】 原因・症状・治し方を医師が徹底解説
これらの条件がひとつでも欠けてしまうとなかなか満足のいく睡眠は得られません。不思議なことに睡眠の量、質共に十分であっても不眠を訴える人がいますし、寝付きがよくないのに不眠を訴えない人もいます。
不眠であるかどうかは、個人差が大きいのも問題を複雑化させてしまう理由です。これは、朝、目覚めるときの気分、体の調子などによって得られる満足感が異なるためです。
睡眠に対する要求が強ければ強いほど、実際には十分眠っているケースがあります。また、必要以上に不眠を恐れてしまう「不眠ノイローゼ」や「不眠恐怖症」という症状もあります。
5人に1人が眠れないという現代では、この割合が多いのかもしれません。日本は、戦後めざましい高度成長を達成し、その一方で現代社会は、複雑化しています。
ストレスの中で生きているといっても間違いないでしょう。文化の急速な発達も眠れない人間をつくってしまっている原因です。
人間は、24時間のうちを7~8時間眠って過ごすのです。30%も寝て時間を過ごしているのです。人間がいかに眠るか?というキーワードは重要です。
医学の進歩で脳波の診断に寄り、客観的な診断もできるようになりました。
ところが本人の主観的な側面が大きく医学の診断と乖離してしまう場合もあります。
このことが治療を行っていく上で最も重要だということをしっかり認識しなければなりません。
不眠症の主な4つのタイプ(症状)
不眠症の症状は、主に以下の4つのタイプに分けられます。
- 入眠困難(寝つきが悪い)
- 床に入ってから30分〜1時間以上、なかなか眠りにつけない状態。
- 中途覚醒(途中で目が覚める)
- 一度眠りについても、夜中に何度も目が覚めてしまい、その後に再び眠りにつくのが難しい状態。
- 早朝覚醒(朝早く目が覚める)
- 希望する起床時間よりかなり早く目覚めてしまい、その後は眠れない状態。高齢者に多く見られます。
- 熟睡感の欠如(眠りが浅い)
- 睡眠時間は足りているはずなのに、「眠った気がしない」「ぐっすり眠れていない」と感じる状態。
不眠症の主な原因
不眠症の原因は多岐にわたり、一つだけでなく複数の要因が関係していることが多いです。
- 精神的・心理的要因
- 仕事や人間関係、家庭環境などによるストレスや不安。
- うつ病や適応障害などの精神疾患。
- 身体的要因
- 痛み(関節リウマチなど)、かゆみ(アレルギー疾患など)、頻尿(前立腺肥大など)、咳や発作(呼吸器疾患)など、身体の病気に伴う症状が睡眠を妨げる。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)やレストレスレッグス症候群(むずむず脚症候群)など、睡眠関連疾患によるもの。
- 環境要因
- 騒音、光、寝室の温度や湿度が不快なこと。
- 生活習慣・薬の影響
- 不規則な生活リズム(交替制勤務、時差など)。
- 就寝前のカフェイン(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)やアルコール、ニコチンの摂取。
- 一部の治療薬の副作用(降圧剤、甲状腺製剤、抗がん剤など)。
- 不眠へのこだわり・悪循環
- 「眠らなければならない」という不眠恐怖やこだわりが緊張を生み、かえって眠りを遠ざける悪循環に陥る。
不眠症の治し方・改善方法
不眠症の治療は、まず非薬物治療(生活習慣や環境の改善)が基本となり、それに加えて薬物治療が検討されます。
1. 非薬物治療(生活習慣・睡眠環境の改善)
最も重要で、自力での改善も期待できる部分です。これを睡眠衛生指導と呼びます。
| 分野 | 改善点 |
| 睡眠リズム | 毎日同じ時刻に起床・就寝し、体内時計を整える。休日もできるだけ平日と同じ時間に起きる。 |
| 起きたらすぐに日光を浴びる。朝食をとることも心身の覚醒を促す。 | |
| 寝る前 | 🍷 寝る前のアルコール、カフェイン、ニコチン摂取を控える(カフェインは午後4時以降避けるのが目安)。 |
| 寝る1時間前には、スマホやテレビなどブルーライトを発する刺激的な活動を避ける。 | |
| 就寝前にぬるめのお風呂に入る、ストレッチや音楽など、リラックスできる習慣を取り入れる。 | |
| 日中 | 適度な運動を習慣化する(激しい運動や就寝直前の運動は避ける)。 |
| 昼寝をする場合は15~30分程度にし、夕方以降は避ける。 | |
| 睡眠環境 | 寝室の温度(18~23℃)や湿度(50~60%)を快適に保つ。 |
| 外部の光や騒音を遮断し、静かで暗い環境を作る。 | |
| その他 | 「〇時間寝なければならない」というこだわりを減らす。 |
| 眠れない時は無理に布団に留まらず、一度寝室を出てリラックスし、眠気を感じてから再度床に入る。 |
2. 専門的な治療
上記の対策で改善しない場合や、症状が重い場合は、専門の医療機関(心療内科、精神科、睡眠専門医)への相談を検討しましょう。
- 認知行動療法(CBT-I)
- 不眠を引き起こしている考え方や行動パターンを見直すことで、睡眠を改善する心理的な治療法。薬物を使わずに不眠の根本的な改善を目指します。
- 薬物療法
- 医師の判断により、睡眠薬(超短時間型、短時間型、長時間型など作用時間に応じたもの)や、原因となっている精神疾患や身体疾患の治療薬などが使用されます。
- 睡眠薬には様々なタイプがあり、依存性などのリスクを過度に心配せず、医師と相談しながら適切に使用することが大切です。
- 原因となる病気の治療
- 不眠がうつ病や睡眠時無呼吸症候群などの他の病気によって引き起こされている場合は、まずその根本的な病気の治療を優先します。
不眠症は適切な対処や治療によって多くの場合改善が可能です。一人で抱え込まず、不眠が長く続く場合は専門医に相談しましょう。