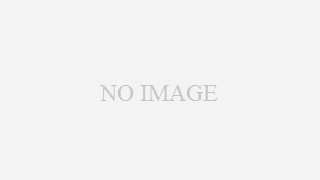 血管
血管 NO をたっぷり効率よく分泌させる 3 つの方法
NO をたっぷり効率よく分泌させる 3 つの方法 を紹介します。NO=一酸化窒素のすばらしさを知るとどうすればくさん出すことができるのか、具体的な実践方法が知りたくなります。 「 NO 力 」 を高めるために必要なこと-それは、ズバリ「血流...
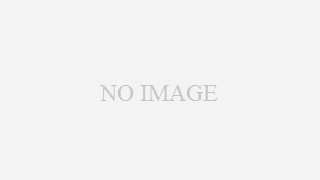 血管
血管 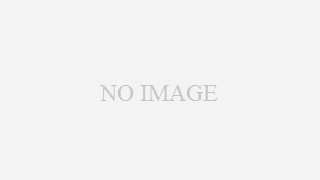 血管
血管 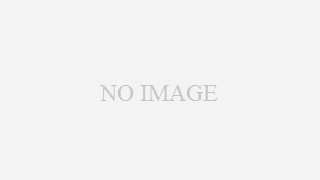 血管
血管