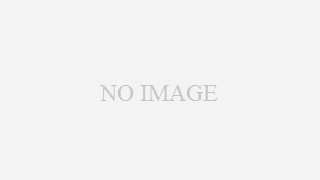 頭痛
頭痛 朝から午前中にかけて特に痛む低髄液性頭痛
あまり聞き慣れない名前の頭痛ですが、低血圧の女性に多く、症状をみると思い当たる人が多いかもしれません。午前中にいつも頭が重くてつらいというときは、このタイプの頭痛が疑われます。 痛み方の特徴 横になっていると痛みが軽くなるか、上体を起こすと...
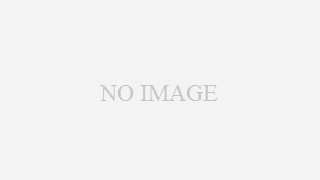 頭痛
頭痛 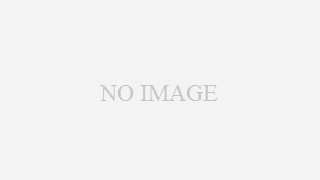 頭痛
頭痛 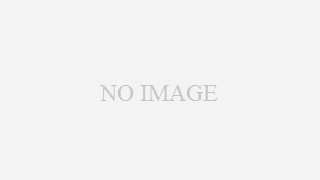 頭痛
頭痛